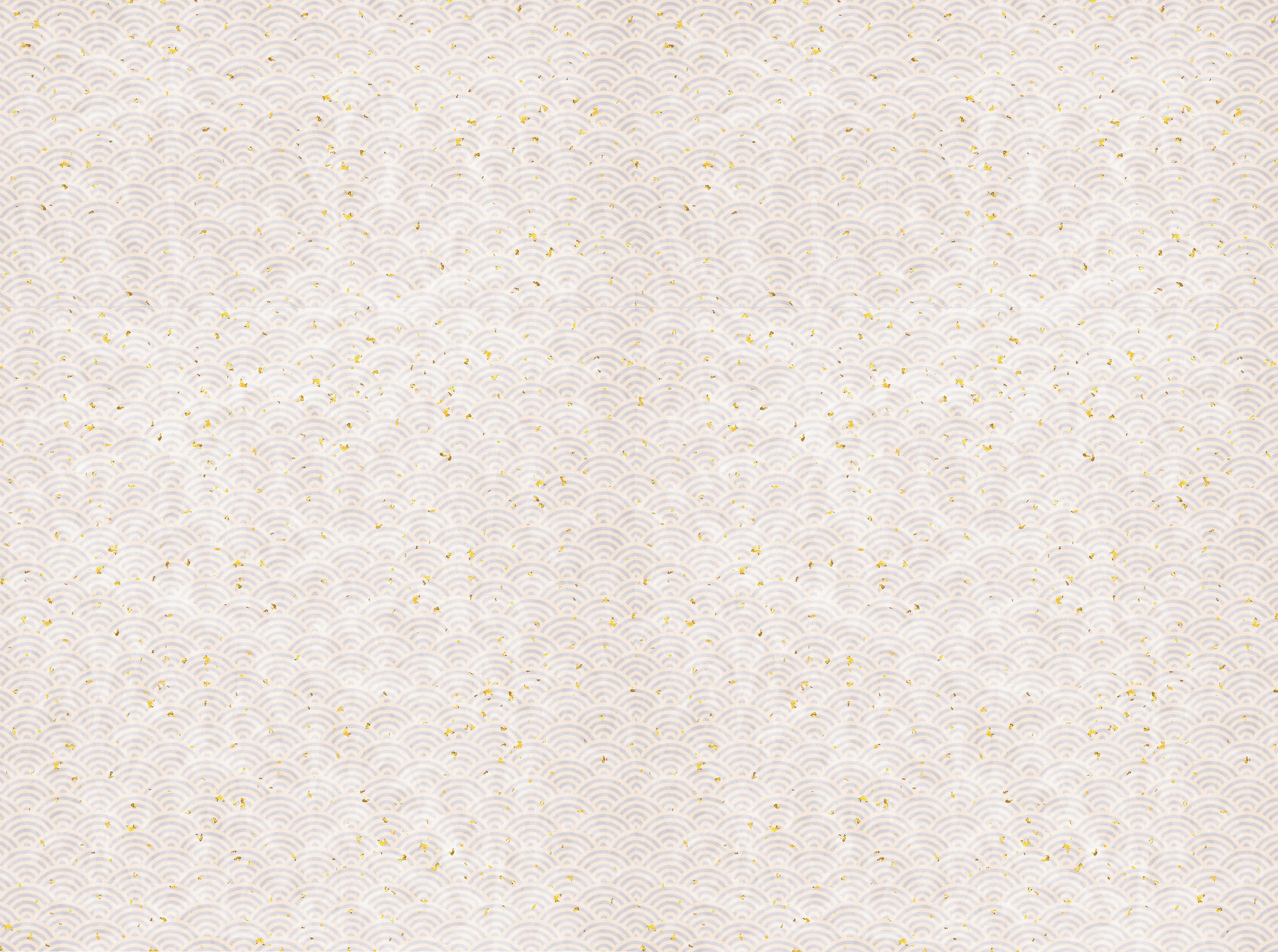
伝統長唄保存会
令和4年度 第12回研修会 2022年9月~11月
令和 4 年度研修は、三本の柱をテーマに企画・構成いたしました。
①地方への発展...北海道・名古屋に続き今回は関西にお願いしました。
②普段あまり演奏されない曲...歌舞伎の元祖と称される出雲の阿国が太閤秀吉の前で歌舞伎踊りを演じてみせる「阿国歌舞伎」を選びました。
③挑戦...「橋弁慶」で長唄と能とのセッションを試みました。
「時雨西行」
指導講師
唄/杵屋 東成・三味線/杵屋 勝禄
〈指導意図 〉
杵屋 東成
この度の研修会は関西地区より『時雨西行』で参加、大勢の方々が研修にお越しになられました。皆さん熱心に毎回お越しになり此方の方もついつい力が篭った指導に成りました。『時雨西行』歌詞の意味 背景 人物 心の表現をどの様に 声 節 間 運びにより表現出来るかを主に稽古して参りました。
短期間の稽古では有りましたが、稽古の成果を思う存分発揮して頂けますことを願って止みません。
杵屋 勝禄
此の度、『時雨西行』の三味線の指導をさせて頂き光栄に思って居ります。この曲の指導に於きまして私なりに、過去諸先輩からの色々教えを乞い、そして又、今私が演奏するに当たって注意すべき諸々の要所を受講された皆様に伝承致しました思いでございます。皆さん、すごく熱心に受講され、気持ち良く指導出来嬉しく思って居ります。
発表会では、その全ての成果の発揮は私でも無理な事、その幾つかでも落ち着いて演奏される事を心より祈って居ります。

■研修生
〈唄〉
杵 家 弥寿厚
杵 家 弥輔橘
杵 家 弥智代
杵 屋 勝欣太
杵 屋 喜美園
杵 屋 喜音嘉
杵 屋 喜代嘉
杵 屋 輝久欧
杵 屋 輝久世
稀音家 加乃葵
稀音家 六加乃
稀音家 六左多乃
東音松浦 麻矢
松 永 忠 翠
松 永 和三津夕
〈三味線〉
今 藤 佐知保
今 藤 佐世佳
今 藤 苗 佐
杵 家 弥津穂
杵 屋 勝欣嘉
杵 屋 勝欣次
杵 屋 勝欣蝶
杵 屋 勘武乃
杵 屋 勘津多
松 永 和三紘野
杵 屋 寛栄佳
稀音家 六三土里
「阿国歌舞伎」
指導講師
唄/日吉 小都女・三味線/日吉 小暎
〈指導意図 〉
日吉 小暎
稀音家浄観先生の作曲で、研精会系の流派では当たり前のように演奏しておりますが、他の流派では殆ど演奏されていないようです。今回のお稽古では、もし踊りがあったとしたら、その場面が目に浮かぶようであって欲しいと思い、場面に合った弾き方を指導させていただきました。全体的にあくまでも綺麗に華やかに、そして楽しく丁寧に演奏して頂く事を望みました。
本来お囃子も入っていますが、この曲の面白さをお聴きいただく為に敢えて今回は素の演奏に致しました。
日吉 小都女
「阿国歌舞伎」のお稽古をさせて頂くに当たって大切な事。これはどの曲も同じですが、まず拍子、間をしっかり取る事。基本に忠実に、音を大事にする事。造作、旋律は基本が有ってこその事、簡単な様で大変難しい事だと思います。唄は声に頼らない、作り声をしない事。これは恩師(先代 日吉小三八師)が常に仰っていた事です。
私もまだまだ未熟ですが、少しでも受講生の皆様に伝わる様にお稽古致しました。流派を越えての演奏に期待しております。

■研修生
〈唄〉
貴 音 日佐世
杵 家 弥江宏
東音海津 志乃
日 吉 あさ衣
日 吉 小都音
日 吉 美 保
〈三味線〉
今 藤 政 玲
貴 音 睦 友
杵 家 七可鷺
杵 家 七 花
日 吉 小 迪
日 吉 知 江
日 吉 八 雲
松 永 忠三郎
吉 住 小十信
「橋 弁 慶」
指導講師
唄/ 東音西垣 和彦・三味線/杵屋 勘五郎・囃子/望月 太左衛・
謡/川口 晃平 副講師/吉 住 小しな
〈指導意図 〉
東音西垣 和彦
今回、松永忠五郎先生、吉住小三代先生からの企画で私に唄の指導との依頼があり能楽師の川口晃平様をお迎えしての長唄とお能の初共演でまさに手探り状態ではありましたが、ある意味指導面も楽しませて頂いた部分もあります。最初の合同稽古の時、川口様のお謡いの声量の凄さに圧倒されました。今回 「橋弁慶」の唄方は女性四人のみですので折角のコラボ演奏、お一人ずつのワケ口を考え、総ヅレで対応し頑張って頂かなくてはなりません。前半の太刀持ちと牛若丸は長唄で、弁慶は能楽で勤めて頂きそのやりとりをどう上手くするか。後半の五条橋のやりとりは長唄が地で能楽師の川口様がそれに合わせて舞って下さるとの事で大変楽しみです。
試行錯誤の連続で大変なお稽古ではありましたが、発表会当日は、舞台客席から楽しみに拝見、拝聴させて頂きます。
杵屋 勘五郎
此の度、能と長唄の共演という企画の講師を仰せつかりました。ご来場の皆様には能と長唄の掛け合いで視覚と聴覚両面を楽しんで頂ければと思います。良くご存知の物語ですから、牛若丸と弁慶、太刀持ち(従者)、夫々のキャラクターの位取り、そして物語の流れを的確に表現しないと期待外れの演奏になってしまいます。曲の解釈を深め三味線と唄の息が揃う事は勿論として、何より能から長唄への受け渡しの間を大切にと心掛けて稽古を進めて参りました。
研修生にとっても初めての経験です。バランスの良い演奏をお聞き頂ければ幸いと存じます。
望月 太左衛
「橋弁慶」を能楽シテ方の先生と共演するという企画の中、能楽・高安流大鼓を安福春雄、安福建雄両師に御指導頂いておりました御縁で囃子の指導をさせていただく事となりました。今回の立鼓・梅屋喜三郎さんは能楽・幸流小鼓の曽和正博師のもと研鑽を積まれていますので能楽囃子同様、小鼓は一人のみとし、大鼓、笛(能管)と共に掛声等能楽の位取りを意識して頂きます。一方、蔭囃子を加え長唄らしい華やかな演奏を目指します。


■研修生
〈唄〉
今 藤 政 透
杵 家 弥江道
松 永 圭 楓
松 永 圭 也
〈三味線〉
今 藤 政光音
杵 屋 勘 紀
杵 屋 勘 華
杵 屋 勘 奈
杵 屋 廣 吉
杵 屋 徳 桜
松 永 裕 子
〈囃子〉
梅 屋 喜三郎
望 月 輝美輔
望 月 大 貴
望 月 太左理
望 月 雪左衛
